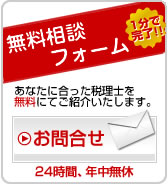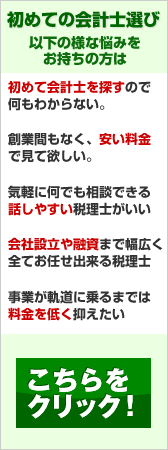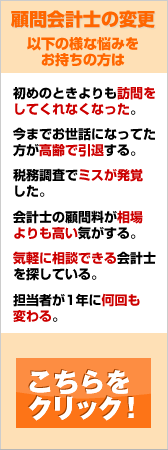トップページ > 会計士と税理士の違いについて
会計士と税理士の違い

 |
税理士 岡野 秀章 氏 平成5年3月 大阪大学経済学部卒業 |
|
会計士紹介センター: 岡野先生、よろしくお願いします。 岡野税理士: よろしくお願いします。 会計士紹介センター: 今回、岡野先生にお聞きしたいテーマは、会計士(公認会計士)と税理士の違いについてになります。 |  岡野税理士 |
岡野税理士:
はじめから結論になってしまいますが、資格としては違いがあるのですが、お客さまにとっての顧問としては同じです。 違いの中でも大きいのは、会計士(公認会計士)は監査(上場企業や学校などの決算書が正しいかチェックする業務) ができるということがあります。
会計士紹介センター:
お客さまの印象としては、公認会計士さんだと敷居が高い。 そして料金も高いというイメージがあるのですが、料金は高いのでしょうか?
岡野税理士:
いいえ、違いはありません。会計士も顧問を受託する場合、税理士として受託するので、 会計士だから高いということはなく、あくまで各事務所の報酬体系の差です。結果として会計士のほうが税理士より安いこともあります。
会計士紹介センター:
なるほど。会計士の資格と、税理士の資格は別々に取得する必要があるんでしょうか?
岡野税理士:
会計士の資格を取ると、税理士の資格も与えられます。ので、別々に取得する必要はありません。
会計士紹介センター:
会計士と税理士の試験科目は違うのでしょうか?
岡野税理士:
以下にまとめてみました。
会計士 |
(すべて必須)簿記、財務諸表論、原価計算、監査論、会社法、経営学、経済学、法人税 |
|---|---|
税理士 |
(必須)簿記、財務諸表論 |
(1科目必須)法人税、所得税 |
|
(2科目選択)相続税、消費税法、酒税法、国税徴収法、固定資産税、事業税、住民税 |
会計士も、法人税の試験があります。また試験科目だけで言うと、すべてをパスした会計士、税理士はいません。
よって試験は、専門家としてある分野の習得レベルをパスできる能力がある者を選抜し、
それにより関連した他の分野も習得すべきレベルに自ら達する能力を有するということを証明するもの、とでもいえると思います。
※なお会計士は2・3年前から試験制度が若干変わりましたが、現時点で独立して会計事務所を開業している者は上記の試験制度をパスした者です。
※実は税理士の半数近くが、税務署などのOB(20数年勤務が条件)で、その方々は試験が免除されます。
 岡野税理士 |
会計士紹介センター: 会計士と税理士の試験合格後の一般的な流れはどうなるのでしょうか? 岡野税理士: 税理士は合格後、会計事務所で2年間の実務経験を経て一人前(税理士として名乗ることができ、また申告書等サインできる) になります。その後は独立して自分で事務所を開業するか、他の会計事務所の職員として勤務するかですが、前者が7・8割だと思います。 会計士は合格後、監査法人(監査を専業として行う会計事務所)で3年間の実務経験を経て、最終試験(ここで法人税の試験があります) を経て一人前になります。その後は監査法人に勤務し続ける人が6・7割くらい、 残りは独立して会計士・税理士事務所を開業するものだと思います。 会計士も独立すると税理士業務を行うことになるのですが、通常の会計事務所の中で、会計士は1割程度ではないかと思います。 |
会計士紹介センター:
会計事務所を開業している会計士は、税理士とは違う業務をメインでやってるのでしょうか?
岡野税理士:
通常8割以上、場合によりすべてが、税理士としての仕事をしています。 会計士は税理士としての資格も与えられるので、独立すると通常税理士として登録して、税理士と変わりない仕事をします。 会計士が専業の監査の仕事は、通常監査法人が行いますし、最近では個人では受託できないと言う会計士業界の自主規制もあります。 なお独立した会計士独自の仕事は、会社法上の大会社や学校などの上場企業以外の監査、株式評価、デューディリジェンス(財務内容調査)、 事業再編コンサルティング、自治体等の監査委員や学識経験者としての委員などがあると思います。
会計士紹介センター:
顧問を選ぶときに、会計士か税理士かを考慮したほうがいいのでしょうか?
岡野税理士:
資格の違いはたいして差異はないと思います。やはり、その人の経験、経歴、人柄、相性、 そしてホントに大事なのがお客さまに役に立とうとする意欲・意識、専門家として継続して勉強していくという意識・意欲だと思います。 “お願いする”のではなく“採用する“という感覚で選んでいただければいいと思います。あと何をお願いしたいかを明確にすべきだと思いますし、 逆にお客さまにとって会計士、税理士が顧問として何ができるかを確認することが大事だと思います。 それから、通常の担当者が会計士、税理士ではない他の職員(その職員が会計士・税理士である場合もある)の場合は、 その担当者の資質も重要になりますし、また会計事務所としての組織体制 (業務にかかるチェック体制、スキルレベルアップの取り組み方針等)も重要になると思います。
会計士紹介センター:
本日は、ありがとうございました。
岡野税理士:
ありがとうございました。